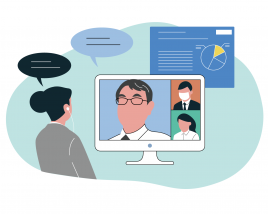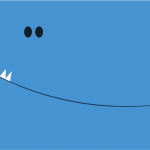2020年10月19日に開催された内閣府規制改革推進会議 第1回 医療・介護ワーキング・グループにおいて、弊社から説明したSaMD開発促進における課題の後半は、規制当局の承認体制及び承認プロセスに関するものになります。
続きを読む規制改革推進会議で取り上げられた医療機器プログラム(SaMD)の開発促進における課題-前編-
2020年10月19日、内閣府規制改革推進会議においてSaMD(医療機器プログラム、Software as a Medical Deviceの略)がテーマとして取り上げられ、河野太郎規制改革担当大臣のもと、民間からの提言に基づき議論が行われました。民間からの説明者として弊社も参加しましたので、どのような提言がなされたのかについて、本記事でご紹介します。
続きを読むセキュリティの観点から考えるオンライン診療サービスの選び方
2020年4月に厚生労働省から発出されたオンライン診療に関する事務連絡(1)により、診療だけでなく服薬指導もオンラインで完結することが可能になりました。オンライン診療の活用が進む要因となり、多くの医療機関でオンライン診療サービスの利用開始が進んでいます。オンライン診療のサービス提供形態には、オンライン診療に特化したサービス(オンライン診療専用サービス)と、既存のビデオ通話システム(汎用サービス)を活用したオンライン診療の大きく2つがありますが、どのシステムを採用したらよいかわからないと悩む医療機関の声をしばしば耳にします。
続きを読むドコモ口座の不正出金問題に学ぶ医療業界のセキュリティのあり方
2020年9月、NTTドコモの「ドコモ口座」を経由した不正出金が発覚(1)し、多くの被害者が出ました。また、いくつかの他の金融機関でも同様の不正出金のインシデントが発生しています。セキュリティがしっかりしている印象の強い国内の金融業界でおきたこの事例を踏まえて、医療業界のセキュリティを確保するためにには何が必要かについて考察したいと思います。
続きを読むApple Watch Series 6の新機能は医療機器になるのか?
2020年9月18日、Apple Watch Series 6の発売が開始されました(1)。Apple Watch Series 6には、血中酸素飽和度(以下、「SpO2」という。)を測定するパルスオキシメータ機能が搭載されたということで、大変話題となっていますが、この機能について、Apple社は「この機能は、医療での使用や医師との相談または診断を目的としたものではなく、一般的なウェルネスとフィットネスのためだけに使えます。」とホームページ上で記載しています。これは一体どういうことなのでしょうか?
続きを読む未来のバーチャル治験を考えてみよう
過去2回の記事では、国内外におけるバーチャル治験、特にオンライン診療の動向を紹介してきました(1)(2)。今回は、より長期的な視点で、DXが進んだ未来におけるバーチャル治験のイメージを描いていきます。その上で、未来の理想像と今のギャップを整理していきたいと思います。
続きを読むApple Watch ECG appの国内承認から見る「医療機器プログラム」
2020年9月7日、デジタルヘルス領域で気になるニュースが入ってきました。2018年に米国で展開開始されたApple Watch ECG appが「Appleの心電図アプリケーション」「Appleの不規則な心拍の通知プログラム」という製品名で、日本でも医療機器として認可(2020年9月4日付)されていたことが公益財団法人医療機器センター(以下、「JAAME」という。)の医療機器承認速報により判明したためです。なお、本件については、JAAMEより公式声明がでていますのでこちらも合わせてご確認ください(1)。
続きを読む国内の医療情報セキュリティに関する歴史 〜 3省3ガイドラインを中心に
医療情報(を含む個人情報)は個人情報の中でも機微な「要配慮個人情報」に該当し、その価値は1件あたり数万〜数十万円ともいわれています。また、医療機器へのサイバー攻撃による事故は、人命に直結しうるため、誤作動や予期せぬ停止は絶対に起こってはならないことです。
昨今、医療情報及び医療情報システムはサイバー攻撃のターゲットになっており、海外では2015年にシンガポールで欧首相含む150万人の情報流出(1)するなど多くの事例が起こっています。国内でも2018年に電子カルテシステムがランサムウェアに感染して1,000名以上の電子カルテデータが閲覧できなくなる(2)など、国内外問わず予断を許さない状況となっています。
今回の記事では、日本の医療業界におけるサイバーセキュリティの取組について、ガイドラインの歴史についてご説明し、海外との比較、他業界との比較、といったテーマを次回以降の記事で取り扱っていきたいと思います。
続きを読む日本における治験へのオンライン診療の導入状況と今後の方向性
前回のコラム(1)では、バーチャル治験の概要と、その中における治験におけるオンライン診療に関する世界の規制や導入事例をご紹介しました。今回は国内にフォーカスをあて、オンライン診療を用いた患者中心の治験について、規制の動向やオンライン診療の導入の方向性を考えていきます。
続きを読むバーチャル治験、知っていますか?〜臨床試験のDXについて〜
バーチャル治験、という言葉を耳にしたことはあるでしょうか?新型コロナウイルス感染症(以下、COVID-19)の拡大により社会は大きな影響を受けており、日々の生活の中へソーシャルディスタンシングやリモートワークといった新しい行動様式を取り入れていく変化が求められていますが、この変化はヘルスケア領域における医薬品の研究開発においても例外ではありません。
続きを読む